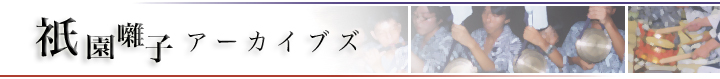4 囃子の機会
ここでは、囃子方の活動について、祭礼を中心にみていくことにする(日程・時間等については、主に2006年の実見にもとづく)。
4月中に放下鉾祇園囃子保存会の役員会を開催し、5月に日程を発表する。そして、現在では6月から、会所の二階でおこなう囃子の練習である「二階囃子」をおこなう(第2・4土曜日、午後4〜7時)。このことにより、以前より二階囃子の日数が多くなっている。これは練習の機会をできるだけ多くした方が良いという考えによる。昔は、吉符入りから鉾がたつまでの間(7月1〜8日)の7日程度のみが、練習の機会としての二階囃子であった。なお、放下鉾においては、現在祇園祭りの一部の所でおこなわれている、毎月定例の練習会等はおこなっていない。

〔写真6〕 二階囃子

〔写真7〕 新入りの囃子方の紹介
7月1日は、山鉾巡行の無事を祈願する「吉符入り」である。囃子方の代表も出席する。この日の夜より、正式の「二階囃子」となる(7月6日まで、時間は午後6時30分〜9時30分、土・日曜日の場合は、午後4〜7時)。7月1日の二階囃子には、新しく入会した子供のお披露目をおこなう。囃子方の幹部らは「一生やることを教えとしてやりなさい」などとさとす。二階囃子での楽器編成は、鉦 10、太鼓 4、笛 10程度である。現在は囃子を30分はやして、15分休むというパタンを3回くりかえす形でおこなっている。なお、昔は現在の練習よりも、1回の時間がとても長く、1時間もつづけてはやしたという。長老の1人は幼少時に、太鼓方のシンが次曲の名称を伝達する際の節回しになぞらえて(「6 演奏の実際」参照)、「やっとこお次はなんじゃい」とおもいながら、ねむたくなってしまったと回想している。
二階囃子の期間中、1日の練習がおわった際に、太鼓を会所の梁からつりさげておく。これは、太鼓を乾燥させるためであるという(写真8参照)。また、二階囃子の練習の後は、仕出し弁当をとって、大人も子供も会食をする機会がある。こうした食事会は、6月と7月の稽古の際にそれぞれ2回ずつおこなう。放下鉾においては、こうした会食をコミュニケーションの機会として重視している。子供の顔をおぼえられるし、子供の躾(礼儀作法)ができるからである。

〔写真8〕 会所の梁につるした太鼓

〔写真9〕 二階囃子終了後の食事会
放下鉾では2007年より、二階囃子の一般人を対象とした見学会を実施している。これは、祭りをよりひらかれたものにしたい、祭りをもっとしってほしい、囃子方の数を拡大したい、といった意図によるものである。2007年は、7月1〜6日の6日間おこない、毎回25名程度の参加者があった(往復はがきによる事前申し込み制)。

〔写真10〕 二階囃子の一般公開
また二階囃子の期間の日中に、中京区のモヨギ幼稚園の園児達をまねいて、囃子にしたしんでもらう機会をつくっている。2006年は7月4日の午後12時30分より、園児約70名、保護者約30名が参加した。鉦を自由に手にもってうってもらったりする。さらに、二階囃子の終了後から鉾立ての間に、料亭のはり清(大黒町五条下)に出囃子(後述)に出向くことが、このところの恒例となっている。
7月13日は、鉾の試し曳きである「曳き初め」をおこなう。新町通りの北観音山・南観音山・放下鉾は、昭和41年(1966)年から合同で曳き初めをおこなっている。午後3時に会所を出発し、四条新町までひくと、今度は北へあがり、新町六角から会所までもどる。所要時間は1時間程度である。曲目の選定は、前述のようにその日の太鼓方のシンの裁量である。

〔写真11〕曳き初め:鉾にのりこむ

〔写真12〕曳き初め:太鼓

〔写真13〕曳き初め:鉦
曳き初めの日の午後7時(以前は7時30分)から、鉾の上で囃子をはじめる(以前は、「鉾囃子」という呼び方をしたという)。以後の開始時間は、14・15日は午後6時30分、宵山の16日は、午後6時からとなり、1日あたりの回数も4回から5回とふえていく。

〔写真14〕宵山における鉾の上での囃子
2006年7月のタイムスケジュール
- 13・14日
- 第1回 午後6時30分〜7時5分
- 第2回 午後7時30分〜8時5分
- 第3回 午後8時30分〜9時5分
- 第4回 午後9時30分〜午後10時
- 15・16日
- 第1回 午後6時〜6時35分
- 第2回 午後7時〜7時35分
- 第3回 午後8時〜8時35分
- 第4回 午後9時〜9時35分
- 第5回 午後10時〜午後10時30分
宵山の16日は、午後10時30分頃まで鉾の上で囃子をはやす。囃子の終了後引き続き、翌日の巡行の晴天を祈願する「日和神楽」をおこなう。放下鉾においては、鉾の上で囃子と「日和神楽」の行事が連続していることに特色がある。すなわち、囃子終了後直ちに、囃子方達が楽器を手にして〈日和神楽〉をはやしながら、鉾から会所の2階に、更には階下におりていく。そしてそのまま町内一回りに出発し、つづいてお旅所にむかう(日和神楽における曲目の詳細については、「3 曲目と笛の旋律パタン」の「曲目の構成」の項を参照)。なお、昔年寄りは、〈日和神楽〉の曲が「明年の明年の」ときこえるとよくいったものだという。
約1時間半後に日和神楽からかえってきてから、鉦に水をはる。これは鉦をひやすためであると同時に、「長い間ありがとう。明日はよろしく」という思いもこめられていると担い手はかんがえている。たとえ一滴でも水をいれるべきものであるとされる(写真19参照)。

〔写真15〕日和神楽:鉾からおりる

〔写真16〕日和神楽:会所の階段をおりる

〔写真17〕日和神楽:町内

〔写真18〕日和神楽:お旅所

〔写真19〕鉦に水をはる
7月17日は、「山鉾巡行」である。鉾を町内の境(錦通り寄り)に移動させてから、囃子方は梯子でのりこむ。巡行時には、鉾がとまると、囃子は一旦とまる。巡行中、囃子方は基本的には鉾からおりることはない。前述のように放下鉾では、巡行時の曲目はほぼきめられている(曲目の選択については、「3 曲目と笛の旋律パタン」の「曲目の構成」の項を参照)。巡行終了後、近隣の料理店で囃子方のお疲れ様会をおこなう。これは若い人がヴェテランに、囃子の構造についての話をきくなど、交流の良い機会となっている。

〔写真20〕山鉾巡行:辻回し

〔写真21〕山鉾巡行:笛方
7月18〜23日にかけて、「御旅所奉納囃子」をおこなう。これは囃子をもっている山鉾のAB2つのグループが隔年でおこなうもので、6月におこなわれる囃子方連絡会での抽選できまる。また、7月24日は「花傘巡行」に参加する(10年に1回)。
7月末から8月頭に、幹部会(放下鉾祇園囃子保存会の成年)のメンバーによって、慰労会に相当する「足洗い」をおこなう。また、12月には、同じメンバーによって、「忘年会」をおこなう。
祭礼以外の機会に囃子をはやすことを、「出囃子」とよぶ。年に2、3回である。ライオンズクラブなどの公共性のあるものや、二階囃子後の料理屋における恒例のものなどにかぎっている。最低15名は必要である。なお、40年程前に、7月24日の花傘巡行の後、泊りがけで天神祭りに参加したことがある。朝日新聞の船にのって、船渡御でも祇園囃子をはやした。むこうのだんじりは鉦が大きく音も大きいので、その点では苦労したという。

〔写真22〕料亭での出囃子(写真提供:永井崇博氏)