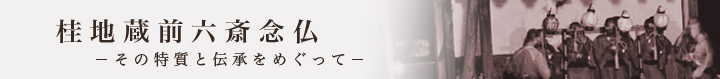2 桂地蔵前六斎念仏の民俗芸能誌
演目とその構成
京都の六斎念仏においては、冒頭に発願念仏を、結尾に回向念仏を配置し、その間に太鼓物(その曲趣を太鼓の芸で演じる)と芸物(所作事や曲芸など)を多数おりこんでいく、一種のバラエティーという構成をとる〔芸能史研究会 1979:20〕。桂地蔵前六斎念仏の場合も同様であり、冒頭の〈発願念仏〉、結尾の回向念仏(〈あみだ打ち〉(一般の場合)、〈地蔵ぶち〉(六地蔵の場合)、いずれも現在はおこなわれていない)の間に、太鼓物と芸物を配置している。
その構成は、「冒頭の太鼓の合図─〈発願念仏〉─〈道行き〉─〈青物づくし〉」までが一連の流れで一組となっており、および最後の「〈石橋〉─〈獅子太鼓〉─回向念仏(〈あみだ打ち〉(一般の場合)、〈地蔵ぶち〉(六地蔵の場合)」も一続き続きになっている。その他の演目の順番はほぼきまっているが、近年は演者の都合(特定の演目の演者が仕事の都合などでおくれてくる等)でかなりの裁量があるものになっている。また、特定の機能をもったものとして、舞台回向当日の開始前に、町内を一回りし開始をつげる際の〈寄せ太鼓〉や、曲と曲の間にうつ幕間の曲である〈カラカミ〉がある(いずれも太鼓の独奏)。さらに、〈しゃしゃらか〉〈玉川〉〈熊坂〉のように、現在伝承がとだえた演目もある。
現在は、伝承している演目がかぎられていたり、演者がそろわなかったりするため、〈四つ太鼓〉で時間をうめていることもあって、全体を約1時間で演じているが、かつては全部演じるのに2時間以上かかったという。聞書きによって再構成した標準的な構成と、主に『桂六斎念佛台本書』(昭和11年9月1日、謄写版、後述)にもとづく、役名・採り物・楽器構成を一覧にしたものが、表1「桂地蔵前六斎念仏の演目構成」である。
| 演目名 | 役名・採り物 | 楽器構成 | 備考 |
|---|---|---|---|
寄せ太鼓 |
大ドロ1 | ||
冒頭の太鼓の合図 |
大ドロ1 | ||
発願念仏 |
一丁鉦4、堅太鼓(表打ち1、カ持約10) | 一丁鉦は凸面打ち | |
道行き |
笛2〜3、一丁鉦4、堅太鼓(表打ち1、カ持約10) | ||
青物づくし |
笛2〜3、鉦、堅太鼓(表打ち2、カ持約7〜8)、中ドロ1、大ドロ1 | ||
観世ぶち |
鉦、中ドロ | ||
式三番叟 |
舞人2(それぞれ鈴1、扇1) | 笛1、二丁鉦2、小鼓、大皮、中ドロ1 | |
豊年踊り (かっぽれ) |
舞人4、5(頬かむり) | 笛2〜3、二丁鉦2、大ドロ1 | |
祇園ばやし |
棒振り1、オカメ・ヒョットコ1 | 笛1、一丁鉦4、中ドロ2(3) | 一丁鉦は凹面打ち
|
四つ太鼓 |
打ち手数人 | 笛1、二丁鉦2、中ドロ4個1組 | |
お公卿踊り |
舞人2 | 笛2〜3、二丁鉦2、中ドロ1 | |
娘道成寺 |
舞人1(扇、ぶち、しもく)、和尚1(扇、数珠)、小坊主2(それぞれ中ドロ) | 笛2〜3、二丁鉦2、中ドロ(陰打ち) 2、大ドロ2、小太鼓1 | |
南瓜 |
舞人2 | 笛1、鉦1 | |
越後晒し |
舞人2(晒しを2枚ずつ) | 笛2〜3、二丁鉦2、堅太鼓2、中ドロ2 | |
土蜘蛛 |
蜘蛛1(巣3面分)、頼公[頼光]1(刀) | 笛2〜3、小太鼓 | |
八兵衛晒し太鼓 |
笛2〜3、二丁鉦2、中ドロ4、大ドロ1 | ||
猿廻し太鼓 |
猿1、猿廻し1 | 笛2〜3、二丁鉦2、堅太鼓(表打ち1、カ持約10)、大ドロ(陰打ち)1 | |
石橋 |
白獅子親1、赤獅子子1(各ぼたんの花1、かんざし1、鼓1) | 笛2〜3、二丁鉦2、小鼓(陰打ち)2、堅太鼓1、小太鼓1 | |
獅子太鼓 |
笛2〜3、二丁鉦1、中ドロ4 | ||
獅子太鼓(「獅子の地廻り」) |
笛2〜3、二丁鉦1、大ドロ1 | ||
あみだ打ち |
中ドロ4 | (一般の場合) | |
地蔵ぶち |
中ドロ4 | (六地蔵の場合) | |
観世ぶち |
中ドロ、鉦 | 不詳 | |
カラカミ |
二丁鉦2、大ドロ1 | 曲と曲の間の曲 | |
〔伝承がとだえた演目〕 |
|||
しゃしゃらか |
舞人2 | 笛1、鉦1、中ドロ2 | |
玉川 |
笛、太鼓、三味線 | 〔田中1959:36〕 | |
熊坂 |
舞人1(長刀) | 不詳 | 日露戦争時に創作 |