伝音アーカイブズ
音曲の流れと五十音図の変遷
| はじめに | 1.五十音図の変遷について | 2.音図の発生と発展 | 3.音曲で用いられる音図 |
龍城千与枝
2.音図の発生と発展
五十音図は、通説では、サンスクリット語の音韻体系をとりいれて、日本語の音韻を並べなおしたもの、といわれている。『伊呂波仮名』のように、四十七文字の仮名文字が生まれたのも平安時代ならば(いろは歌は、空海によって整理されたといわれている。)、ア行からワ行、ア段からオ段までの五十の音が完備した『五十音図』が完成したのも、平安時代のこと。平安時代といえば、中国との文化交流が盛んで、漢字が輸入され、仏教が国教として広まった時期である。遣唐使として唐にわたった留学僧たちの間では、持ち帰った経典の意味を解明しようとする「音義」の研究がはじまっていた。当然ながら、それらの学問研究は国をあげて取り組まれた一大事業であった。一方で、日本古来の文化を振り返り、大和言葉の音図を意識する動きも高まっていたといえる。
国語学者の山田孝雄(よしお)は、平安時代末期の歌学研究で「音の相通関係」が発見されていたことを、『五十音図の歴史』の中で明らかにした。藤原範兼が、歌を声に出して詠むときに、ある文字とある文字(たとえば「り」と「れ」、「ひ」と「は」など)が「同こゑ」、「かよふ聲」であるとしている。これは、みてのとおり、子音の発見となる。音の相通関係については、古代から認識されており、『古事記』や『日本書紀』『風土記』にもみえる。しかし、このような発見は、体系化には至らなかったようだ。
さて、同時期の音義研究においても、日本最古とされる音図が残されているので、その内容をご紹介したい。
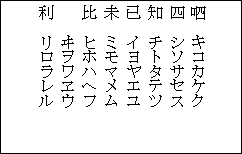
これは、醍醐寺に残されている『孔雀経音義』に、万葉仮名で手書きされたものを通字体に戻した表である。『孔雀経』とは、唐の三蔵法師が伝えた経典で、『孔雀経音義』は、原語である中国語の解釈と読み方を記した書である。音図の書き込みは平安中期の写本にのこっており、平安後期の筆と推定されている。一見してわかるように、並べ方は現在のアイウエオ順とは異なっている。またア行とナ行がかけており、五十の音には満たないのが特徴的である。これらの点から、平安末期までは、一般的に、音韻研究としての音図研究はなされていたが、現在のような五十の音に厳選されることはなかったと考えられている。
このような中で、五十音図を完成させていったのは悉曇学といわれる、密教の呪文であるところの梵語を学ぶ学僧たちであった。密教は、インドから中国を経由して日本に将来されたが、その過程でいくつかの流派がわかれた。それを統合的に体系付けたのが、『悉曇蔵』を表した天台系の僧侶安然であった。その経典についての学問は、サンスクリット語で、釈迦を表すシッダムの訳語に、祝福するという意味の「曇」の字を当て、「悉曇学」と名づけられ、江戸中期まで続いた。
サンスクリット語である梵語は、すでに奈良時代に日本に伝わっていたとされる。しかし、それを教義とともに本格的に将来したのは、弘法大師空海といわれている。ことに、真言や陀羅尼といった梵語の呪文を唱えることが宗義のひとつであった密教では、その一つ一つの文字の発音に形而上的な意味をもたせる宗義があった。このため、僧侶たちは、梵語の正しい発音を求め、サンスクリットの音韻体系を参照しながら、「梵字の五十音図(悉曇章)」を完成させたのである。(詳しくは、大正新脩大蔵経84巻『続諸宗部 悉曇部』所収の『悉曇要訣』「悉曇章(梵字の五十音図)」をご参照ください。)
一方、江戸時代になると、日本では漢学の研究が盛んになり、漢詩の押韻を理解したいという欲求が深まった。韻学の研究はこうした欲求から始まり、本居宣長によって大成された。鎌倉時代初期に中国から輸入された『韻鏡(いんきょう)』は、唐音(唐末の中国語の発音)を「音」と「韻」に分けて考えた中国の音韻表であった。江戸時代の国学者本居宣長は、この表から「押韻」の理屈を理解し、やがて昔からあった五十音図(図1)を日本語の音韻表と認識して、音韻を整理した(図2)。その後、『俚言集覧』の著者でもある太田全齋によって書かれた『漢呉音図』でアイウエオの表を整理しなおしている。アイウエオ、ヤイユエヨ、ワヰウヱヲを音韻どおりに並べ替えてあるのが特徴的である。冒頭に挙げた明治期の『国字五十音』では、このような経緯をたどって、音韻の相通から、母音を考え直した結果として整理された表なのである。

音韻の相通から、母音を考え直した物、ア行の「ヲ」とワ行の「オ」をいれかえるきっかけとなる。
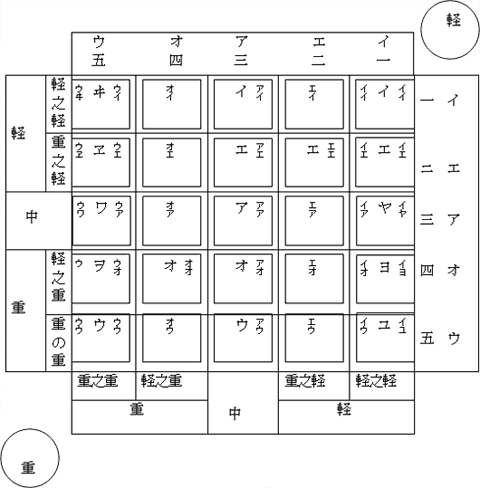
五十音の変遷をたどっていくことで、冒頭にあげた、明治期の「国字五十音」のような表が、こうした過程で生まれたことは理解できよう。しかしながら、国学派が解釈したものは、あくまで表であり、音図とは異なっている。すなわち、音図の場合は、図であって、音がでる地点(調音点)のマッピングでしかない。そのため、『悉曇章』や、その系統にあたるそれまでの五十音図をご参照いただければわかるように、ひとつの枡のなかに、拗音と呼ばれる、複数の音が並存するという特徴が生まれるのである。
- 伝音アーカイブズ
-
- 資料展示の記録・解説
- 音曲の流れと五十音図の変遷
- 昭和の美学書としての『日本音楽の性格』について
- 収蔵資料検索